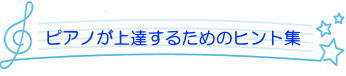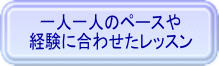ひとりごと №2
日ごろから思っていること、感じたこと、ピアノを学ぶ上で大切なこと、
ピアノを演奏する上で大切なこと。。。等
少しずつ書いていきたいと思っています♪
メニューへ
![]()
![]() 静岡市駿府公園の紅葉
静岡市駿府公園の紅葉
![]() 綺麗に弾けるピアノ奏法・重力奏法
綺麗に弾けるピアノ奏法・重力奏法
倍音を綺麗に鳴らす奏法について
![]() T君ありがとう!
T君ありがとう!
![]()
![]() 桜と菜の花
桜と菜の花
![]() ジョウビタキ
ジョウビタキ
![]() 2017年 ご挨拶
2017年 ご挨拶
![]() 山寺(宝珠山立石寺)
山寺(宝珠山立石寺)
![]() アカゲラのお父さんとお母さん
アカゲラのお父さんとお母さん
![]()
静岡市駿府公園の紅葉
12月初めに、静岡市中心部にある駿府公園へ紅葉を見に行ってきました。
イチョウの紅葉が見ごろで、黄色が輝いてとても綺麗でした。

こちらは、駿府公園内にある紅葉山庭園です。
青空だと良かったのですが、ちょっと雲が出てしまいました。




公園に戻ると、黄色と赤の紅葉が混ざった木を発見!

夕方の斜光が当たり、とても綺麗に輝いていました。

紅葉は、アルプス等の高い山では、9月には見頃を迎えます。
それから段々と標高の低い所へと降りてきて、暖かい静岡市街地では、12月に紅葉の見頃を迎えます。
今年は寒暖の差が激しかったせいか、静岡市街地の紅葉もとても綺麗でした。
そういえば、10月の連休に東北に行き、盛岡インターで東北道を降りたのですが、盛岡インター周辺の紅葉がとても綺麗でした。
イチョウの黄色とナナカマドの赤のコントラストがとても素敵でした。
走行中で写真が撮れなかったのが残念ですが。。。
高度の差だけでなく、緯度の差でも、紅葉の時期がこれだけ違うのです。
ちなみに、ナナカマドは、静岡辺りでは高い山にしか生えていませんが、東北や北海道では街路樹として植えてあるのですよ。
日本は小さい島国ですが、縦に細長いので、気候の差が大きいですね。
だから、いろいろ楽しめますね!
| 2017.12 |
![]()
![]() 綺麗に弾けるピアノ奏法・重力奏法
綺麗に弾けるピアノ奏法・重力奏法
倍音を綺麗に鳴らす奏法について
ピアノには、沢山の魅力がありますね。
その沢山の魅力の中の一つに、音の響きがあります。
ピアノは、タッチの仕方やペダルの使い方等、弾き方(奏法)を工夫し、倍音を豊かに綺麗に鳴らすことによって、多彩な響きが出ます。
倍音は、それぞれの音に必ず含まれていますので、どんな弾き方をしても鳴りますが、それを綺麗に鳴らす、倍音を生かした演奏をすることが大切です。
では、倍音を綺麗に鳴らす演奏とはどんな演奏でしょうか。
まず、倍音についてですが、倍音は、ある音の周波数の整数倍の音のことです。
元になる音を基音といいます。
ドの倍音は1オクターブ上のド、2オクターブ上のド、順にソドミソ♭シドレミ・・・です。
ドを鳴らすと、これだけの音がドのなかに入っているということです。
人の声も、それぞれの人の声の倍音が違うので違う声になっています。
倍音は、ガンと思い切り鍵盤をたたいても綺麗には鳴りません。
指だけで押し付けるように弾く弾き方でも、音がつぶれてしまい、綺麗に倍音が鳴りません。
聞こえてはきますが。。。
基音中心の音の出し方になってしまいます。
倍音は、タッチの仕方やペダルの使い方等、弾き方(奏法)を工夫すると綺麗に鳴ります。
倍音を綺麗に鳴らすには、微妙なさじ加減のタッチの仕方が大切です。
タッチについては、力まず自然な状態で、腕の重みを指に乗せる感じで弾きます。
手首を柔軟に使うことや、手のひらの使い方、支えも重要です。
指の力で弾くのではなく、指は支えるだけです。
脱力も大切ですが、脱力と言っても、腕や手の力をすべてふにゃふにゃに抜くのではなく、手を支えるために必要な筋肉は使います。
無駄な力を入れないということです。。
このような重みをかけて弾く奏法は、ロシア奏法、重力奏法とも言われています。
この奏法は、体全体をしっかり使って弾くので、体が小さい演奏者でも、深みのある迫力のある音を出すことが出来ます。
芯のある、遠くへ美しく伸びていくピアニシモも出すことが出来ます。
無理をした弾き方をしませんので、音が豊かになり、手も傷めません。
腱鞘炎になることもありません。
綺麗なレガート奏法も、伸びのある音も、この奏法でとても楽に出来るようになります。
倍音を綺麗に鳴らした演奏は、とても綺麗です。
多彩な響きが出ます。
ある音を出して、その上にまた他の音が重なり、それぞれの音の倍音も重なっていくと、音に広がりや奥行きがでて深さを増していきます。
低音を綺麗に響かせ、その上にいろいろな音をお互いの音がけんかにならないように乗せていく。
そのような事を大切にしながらピアノを弾くと大変面白いです
演奏者の魂が、聞いている人の所へ、ぽ~んと飛んでいくような、そんな感じで人の心に届く演奏になります。
世界の一流ピアニストは、この倍音を綺麗に鳴らして弾いています。
また、作曲家でいえば、ショパンの曲等は、倍音がとても美しく鳴るように作曲されていますので、倍音を綺麗に鳴らすように弾くととても美しい演奏になります。
ラフマニノフの曲も倍音が綺麗ですね。
この奏法を生徒達に教え、出来るようになると、皆さん口を揃えて、「綺麗、楽しい、面白い!」と夢中になっていきます。
そのような奏法が出来るように、基本からしっかりレッスンをしています。
ピアノを始めたばかりの幼児さんも、将来的にそのような奏法が出来るように、しっかりとした下積みを、子供さんの年齢、理解度に合わせて丁寧にレッスンしています。
ピアノ経験がある方にも、綺麗に弾ける奏法を分かりやすくレッスンいたしますので、必ず綺麗に弾けるようになっていきます。
皆様、是非、この倍音を綺麗に響かせて、綺麗にピアノが弾ける奏法を体験してみてください。
ピアノの世界が変わりますよ!
| 2017.11 |
![]()
T君ありがとう!
12年間レッスンに通ってくれた高校生の男の子T君が、教室を卒業していきました。
進学校に通いながら、勉強と部活(運動部)とピアノ、3本立てで本当に良く頑張ってくれました。
T君は、教室の年下の子供達の憧れの的で、発表会では、皆、T君の演奏を聞くのを楽しみにしていました。
今年の発表会でも、練習時間が思うように取れない中、大曲に挑戦してくれました。
とても心に響く演奏でした。
T君の少し年下の男の子は、「T君が卒業したら、今度は自分が男子で一番上になるから頑張らないと!」と言っていました。
頼もしいですね!
小さい子供達が、お兄さんお姉さん達の演奏に憧れて、それを目標に頑張って、そのお兄さんお姉さん達が卒業して、また次に続く子供達が、小さい子供達の憧れになる。
なんて素敵なことでしょう!
それにしても、小さくてかわいらしかった子供が、もう立派な高校生、そしてあっという間に大学生になるのですね。
この12年間のT君との思い出が、走馬灯のように頭を駆け巡ります。
時が流れるのは早いものです。
教室はとても寂しくなってしまいますが、これからは、自分の目標に向かって一生懸命勉強をして、夢をかなえて欲しいと思います。
T君、今までありがとう(^^)
| 2017.9 |
![]()
「聞く」と「聴く」
皆さんは、 ピアノを弾く時、ピアノの音を聞いて弾いていますか?
それとも聴いて弾いていますか?
まずは、「聞く」と「聴く」の違いについてですが、
「聞く」は、音が自然に耳に入ってくる、漠然ときこえる等、単に音が耳に入るという聞き方です。
「聴く」は積極的に意識して音に耳を傾ける聴き方です。心を傾けて聴くということ、聞こえるものの内容を理解しようと思ってしっかり聴くという意味があります。
ですので、「ピアノの音を聞いて弾く」というのは、ドレミの音は耳には入ってきているけれど、漠然と聞いているので、自分がきちんと弾けているかどうかが聴けていない状態です。
ただ、指を動かして音を出している状態です。
一方、「ピアノの音を聴いて弾く」というのは、細かいことを注意しながらしっかり聴いて弾けている状態です。
どんな音色で弾けているか、音の響きはどうか、フレーズはきちんと歌えているか、ハーモニーの変化、各声部のバランスはどうか等、いろいろな事に注意して、自分が出している音をしっかり聴いて弾けている状態です。
というわけで、ピアノを弾くときには、音を聞くのではなく、聴くことが大切です。
音をしっかり聴けていないと、心が届かない演奏になってしまうし、綺麗に弾くことは出来るようにはなりません。
ピアノを弾く時は、沢山ある音符や記号を読まなくてはならないし、間違えないように弾かなければと、やらなければならないことが沢山あります。
ですので、つい、指の動きばかりに気をとられてしまい、音は耳には入ってきているけれど、どんな音色で弾けているか、音の響きはどうか、フレーズはきちんと歌えているか、ハーモニーの変化、各声部のバランスはどうか等、いろいろな事に注意して、自分が出している音をしっかり聴くということがおろそかになってしまうことが多いと思います。
メロディーは聴いていても、伴奏は聴いていないとか、主旋律は聴いていても、副旋律は聴いていないとか。。。そのようなこともあると思います。
また、ピアノは、弾いている鍵盤の所で音が出る訳ではなく、その先でハンマーが弦をたたいて弦を振動させて音が出るのですが、そのことをすっかり忘れて、鍵盤での指の動きばかりに気をとられてしまうことも多いと思います。
一つ一つの音を良く聴いて、ハンマーが弦をたたいて音が出ていることを意識して大切に音を出すように心がけていくと、音楽が生きてきます。
自分が出している音をすべて聴けるようになってくると、演奏が変わっていきます。
音に命を吹き込めるようになりますので、演奏が生き生きしてきます。
一つ一つのパートを歌い合って、合奏をしている、そんな感じの演奏にもなっていきます。
ドレミの音がただ耳に入ってきて漫然と弾くのではなく、音色、音の響きはどうかな、ハーモニーは? 各声部の音のバランスは大丈夫かな。。。いろいろな事に注意して、よ~く音を聴いて弾いてみましょう。
素敵な演奏になっていきますよ(^^)
| 2017.6 |
![]()
桜と菜の花


写真は、5月初旬の秋田県八郎潟菜の花ロードの菜の花と桜です。
11キロにも渡って菜の花と桜並木が続きます。
ソメイヨシノ・ヤマザクラ・八重桜の並木です。
延々と続くまっすぐな道路の両側に菜の花と桜が咲いて、その景色は圧巻でした。
この時は、あいにくソメイヨシノは終わってしまいましたが、ヤマザクラと八重桜がとても綺麗でした。
いつか、ソメイヨシノが満開の時にも訪れてみたいですね(^^)
| 2017.5 |
![]()
ジョウビタキ
お散歩の途中で見かけたジョウビタキの雄です。
とっても綺麗でかわいいですね!
ジョウビタキは、雀より少し小さい位の大きさの小鳥で、チベット、中国東北部、ロシア南東部、バイカル湖付近で繁殖し、秋になると日本等に渡って来て越冬する冬鳥です。
春になるとまた繁殖地へ戻っていきます。

この小さな体で、毎年何千キロもの距離を往復するそのパワーに驚かされます。
とても人懐っこく、近くまで寄ってきてかわいいしぐさを見せてくれることもありますよ。
市街地の公園などで見かけることもあります。
以前、駿府公園でも見かけましたよ。
今年は酉年。
鳥達のパワーにあやかり、飛躍の年になりますように!
| 2017.1 |
![]()
2017年 ご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、大きな災害や事件が沢山ありました。
今年は平和な年でありますように。
そして、皆様の所に沢山の幸せが訪れますように!

レッスンに関しては、ピアノってすごい、音楽ってすごいって思っていただける、ピアノを弾くことにわくわくできる、そして一段と上達していく、そんなレッスンを心がけていきたいと思っています。
上の写真は、伊豆沼(宮城県・ラムサール条約登録湿地)でのマガンや白鳥達です。
ここは、渡り鳥であるマガンや白鳥たちの楽園です。
早朝、マガン達は餌場となる田圃へ飛び立っていきます。
何万羽ものマガン達が飛び交っていく様子は圧巻です。
この日は、少しずつ順番に飛び立っていましたが、何万羽が一斉に飛び立つこともあるそうですよ。
近くの田圃では、ハヤブサも見かけました。
鋭い大きな目とくちばしが印象的ですね。
ハヤブサは、獲物を狙って急降下する時の速さは時速200キロを越すとのこと、凄いですね。
時速387キロという測定結果も出たことがあるようで、本当に凄いです。
新幹線の名前に名付けられる理由が分かりますね。
大きさは、カラス位なんですよ。

それでは、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
| 2017.1 |
![]()
山寺(宝珠山立石寺)
11月中旬に、いつか訪れたいと思っていた紅葉の山寺(山形県)に行ってきました。
山寺は、松尾芭蕉の句「閑さや岩にしみ入る蝉の声」で有名ですね。
正式名は宝珠山立石寺といい、貞観2年(860)清和天皇の勅願によって慈覚大師円仁が開いた天台宗のお寺です。
慈覚大師円仁は、平泉中尊寺や松島瑞巌寺、青森恐山等、数多くのお寺を開山された方です。
戦乱に傷ついた東北を鎮めるため布教に心血を注いだと伝えられています。
紅葉と快晴とお休みの土日が見事に重なり、これは行くしかないと、、、
紅葉も景観も素晴らしかったです。
一番紅葉が綺麗だった仁王門です。
「嘉永元年(1848)に再建されたけやき材の優美な門で、門の左右に安置された仁王尊像は、運慶の弟子たちの作といわれ、邪心をもつ人は登ってはいけないと、睨みつけている。後方の閻魔王がこの門を通る人達の過去のおこないを記録するという。」と書いてありました。
過去の行いを記録されてしまうなんて、きちんと生きないといけないですね(^^)

正面から見た仁王門です。

仁王門の少し手前にある「せみ塚と」その奥の岩場です。
芭蕉の句をしたためた短冊をこの地に埋めて、石に塚をたてたとのことです。
この岩場のずっと上に開山堂等のお堂があります。

奥の院
正しくは「如法堂」と言うそうです。
山門から石段を約千段上り切った所にあります。
この約千段の石段は、「一段一段踏みしめていくごとに一つずつ煩悩が消え悪縁を払うことが出来る」とのことです。

変わった岩を発見。
この付近には、このような岩が多いです。

胎内堂
この右上奥に釈迦堂があります。
深い谷の上に鉄製の橋が架かっていて、その先に岩穴があります。
ここが「胎内くぐり」と言われる所で、穴を数メートル這って胎内堂に出ることができるそうですが、今では、修行者以外の立ち入りを禁止しています。

なんと、カモシカが姿を見せてくれました。
通路の対岸の岩場にいました。
色が白っぽくてとても綺麗な、まるで神の化身を思わせるようなカモシカでした。

開山堂
「立石寺を開かれた慈覚大師の御堂で、この御堂が建つ崖下にある自然窟に大師の御遺骸が金棺に入れられ埋葬されています。御堂には大師の木造の尊像が安置されており、朝夕、食飯と香が絶やさず供えられ護られています。」とのことです。
左側の岩の上の赤い小さな御堂は、書写したお経を4年に1度納める納経堂です。
山寺で一番古い社だそうです。

納経堂

開山堂から少し登った所にある五大堂からの眺め
五大堂は、天下泰平を祈る道場だそうです。

下から見た山寺全景です。

望遠レンズで撮ってみました。
左が五大堂、右が開山堂、その右にあるのが納経堂です。

釈迦堂です。

こんな岩場の上に何百年以上も前にお堂を建てたなんて凄いですね。
山寺は、無宗教の私にも、とても魅力的な所でした。
約千段の石段を上る途中にお堂や石仏等が沢山あり、いろいろな表情を見せてくれます。
またいつか、季節を変えて訪れてみたいと思っています。
今回とは違う何かを感じることが出来るかもしれないですね。
| 2016.12 |
![]()
アカゲラ
森を歩いていると。。。
アカゲラのお母さんが巣穴から顔を出していました。
巣穴の中には卵があるのでしょうか。

アップで撮ってみました。

しばらくすると、お父さんアカゲラが帰ってきました。

巣穴から顔を出すお父さんアカゲラです。

後何日か経つと、この巣穴から、かわいい赤ちゃんアカゲラが顔を出すかもしれませんね♪
元気な赤ちゃんが生まれて、無事巣立っていってくれると嬉しいですね。
| 2016.5 |